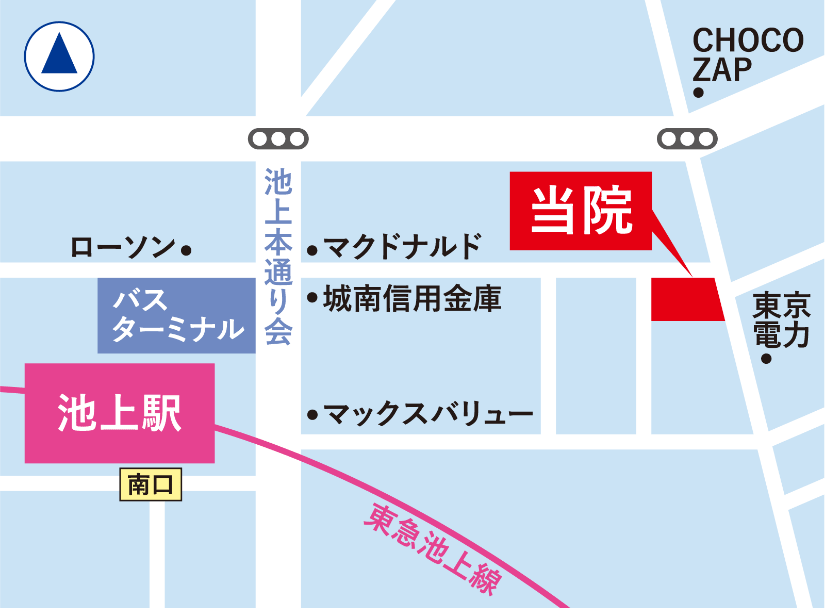当院の循環器内科で扱う主な疾患
心不全
心臓の収縮・弛緩機能が低下してしまい、全身の組織に十分な血液を送り出せなくなっている状態です。これに伴い、様々な症状が起こります。例えば、疲れやすい、だるい、動悸などがみられたときは、心不全の可能性があります。また、うっ血が肺に生じた場合は、息切れや息苦しくなる症状が現れます。これに伴い、体の様々な部分でむくみが現れます。患者様によっては、嘔気、嘔吐、食欲低下などが起こることもあります。
なお、心不全のなかには、心機能が急に低下する「急性心不全」と、心機能が普段から低下している状態にある「慢性心不全」があります。このうち急性心不全の場合は、直ちに治療をしないと、命に関わるケースがあります。患者様の状態を見極めたうえで、酸素吸入を行ったり、心臓にかかる負担を減らすためのお薬を使用したり、血液の流れをよくするためのお薬を使用したりして、まずは症状を緩和させます。その後、原因となる病気の診断が確定したらその治療も行います。慢性心不全の場合も薬物療法が行われますが、結果的に手術療法が必要になるケースも少なくありません。
急を要する病状のこともありますのでお気軽にご相談ください。
不整脈
- このような患者様は当院をご受診ください
- 心房細動・心房粗動・発作性上室性頻拍・心房頻拍・上室性期外収縮・心室性期外収縮・洞不全症候群・心室頻拍・心室細動・ペースメーカー・アブレーション治療後 など
不整脈には様々なタイプがあります。当院では、心房細動・心房粗動・発作性上室性頻拍・心房頻拍・上室性期外収縮・心室性期外収縮・洞不全症候群・心室頻拍・心室細動などの患者様を診療いたします。 急を要する病状も多いためお気軽にご相談ください。
また、ペースメーカー・アブレーション治療後の患者様も当院で対応させていただきます。すでに不整脈の診断を受け、ペースメーカー・アブレーション治療を終えている患者様のうち、その管理が必要な患者様に対して必要な治療を行っていきます。ペースメーカー留置術後の患者様、不整脈のカテーテル治療後(アブレーション治療後)の患者様は、お気軽に当院をご受診ください。
なお、不整脈が発生する主な原因は、冠動脈疾患、心臓弁障害、心不全、先天性心疾患などであり、その多くが心臓に起因する病気です。ただし、はっきりとした心臓の病気がなかったとしても、老化、ストレス、睡眠不足、疲労などによって不整脈が起こることもあります。心臓は1日に約10万回も拍動しており、心臓は時には規則正しくない電気信号により不規則な動きをしてしまう場合があります。
不整脈にはいくつかの分類方法がありますが、一般の方々に分かりやすいものとして、頻脈、徐脈、期外収縮の3つをご説明させていただきます。このうち頻脈は、文字通り心拍数が頻繁になる病気です。患者様の多くは、ドキドキとする動悸を感じるようになります。さらに脈が速まっていくと、心臓が全身に血液を送り出せない状態となってしまい、吐き気や冷や汗、意識消失等の症状が出てきます。これに対し、徐脈は、心拍数が遅くなりすぎる病気です。徐脈になると、フラッとしたり、めまいがしたり、意識が無くなって卒倒したりします。徐脈状態が長い間続くと、動作時に息切れがするようになります。期外収縮は、脈が飛んだり、抜けたりするタイプの病気です。期外収縮になっても自覚症状を感じないことが多いのですが、症状を感じる時は、脈が飛んだり、胸の周辺部分に不快感を覚えたり、胸が痛くなったりします。 急を要する病状のこともありますのでお気軽にご相談ください。
虚血性心疾患
- このような患者様は当院をご受診ください
- 虚血性心疾患(心筋梗塞・狭心症)・経皮的冠動脈形成術後(PCI:冠動脈ステント治療後)・冠動脈バイパス術後(CABG)) など
虚血性心疾患には、狭心症や心筋梗塞などの種類があります。このうち狭心症は、心臓の冠動脈の血流が不足することによって、心筋が酸素不足に陥ってしまう病気です。動脈硬化が進行して冠動脈の血管が狭くなり、心臓への血液の流れが一時的に滞るために発症するケースが多いです。このような状態を放置していると、心筋梗塞など生命にもかかわる危険な状態になるので、狭心症の段階でしっかりと検査・診断・治療しておくことが肝心です。
冠動脈が詰まって血流が途絶えると、心臓の筋肉に酸素と栄養が供給されなくなり、やがてその領域の筋肉が死んでしまいます。このような病気のことを「心筋梗塞」と呼んでいます。主な症状は、激しい胸の痛み、強い圧迫感、呼吸困難、冷汗、嘔吐などです。ただし、高齢者や糖尿病の患者様の場合、胸痛を自覚しないこともあります。
当院では、心筋梗塞や狭心症などの虚血性心疾患の予防・治療をはじめとして、経皮的冠動脈形成術後(PCI:冠動脈ステント治療後)・冠動脈バイパス術後(CABG))の治療やケアについても対応いたします。なお、ここでいう術後の治療・ケアとは、これから虚血性心疾患の診断治療を希望する患者群と、すでに治療を終えた患者群(PCIやCABG治療後群)の患者群を分けるための表記となります。 急を要する病状のことも多いため、お気軽にご相談ください。
心筋症
- このような患者様は当院をご受診ください
- 肥大型心筋症・閉塞性肥大型心筋症・拡張型心筋症・心サルコイドーシス・心筋炎 など
心筋症は、心臓の筋肉に問題が起こってしまい、心臓の機能が徐々に低下してしまう病気です。この中には様々なタイプがありますが、大きく二つに分けられます。一つ目は、心臓弁膜症や高血圧症などの特定の病気によって発症するものであり、「二次性心筋症」と呼ばれます。二つ目は、原因がはっきりしないものであり、「特発性心筋症」と呼ばれます。特発性心筋症には、大きく分けて拡張型・肥大型・拘束型の三種類があります。
拡張型心筋症は、心室が拡大して心室の壁が薄くなるタイプです。肥大型心筋症は、心室の壁が厚くなり、内部が狭くなるタイプです。拘束型心筋症は、心室の壁が硬くなるものの、必ずしも厚くはならないタイプです。それぞれに症状や経過が違い、治療法も異なってきます。当院では、肥大型心筋症・閉塞性肥大型心筋症・拡張型心筋症・心サルコイドーシス・心筋炎をはじめとして、心筋症に対して検査・診断・治療を検討いたします。
弁膜症
- このような患者様は当院をご受診ください
- 大動脈弁狭窄症・閉鎖不全症、僧帽弁狭窄症・閉鎖不全症、三尖弁狭窄症・閉鎖不全症、肺動脈弁狭窄症・閉鎖不全症、弁膜症手術後・TAVI手術後・マイトラルクリップ術後・左心耳閉鎖術後、卵円孔開存症閉鎖術後など
心臓の内部は4つの部屋に分かれており、上の部屋を心房(右心房・左心房)、下の部屋を心室(右心室・左心室)と呼びます。左心室からは全身に血液を供給する大動脈がのびており、右心室からは肺に血液を供給する肺動脈がのびています。この心室と動脈の間と、心房と心室の間には、扉のように開閉する構造物があります。これを「弁」と呼びます。弁膜症は、これらに狭窄や閉鎖不全などが見られる病気のことをいいます。弁膜症は生まれつき先天的に形態的異常がある場合や、加齢による変化、リウマチ熱の後遺症、動脈硬化、心筋梗塞などに伴って生じる場合があります。病気が進行して弁の機能が落ちると、次第に心臓に負担がかかるようになり、動悸、息切れ、疲労感、胸痛、呼吸困難などの症状が出てきます。
当院では、大動脈弁狭窄症・閉鎖不全症、僧帽弁狭窄症・閉鎖不全症、三尖弁狭窄症・閉鎖不全症、肺動脈弁狭窄症・閉鎖不全症などの疾病管理を行います。さらに、弁膜症手術後・TAVI手術後・マイトラルクリップ術後・左心耳閉鎖術・卵円孔閉鎖術後の疾病管理・内服管理についても対応いたします。
動脈瘤など
- このような患者様は当院をご受診ください
- 動脈瘤・大動脈解離・動脈硬化症・大動脈手術後 など
大動脈は人間の体の中で最も太い血管であり、全身に血液を送る役割を担っています。この血管は心臓から上向きに出た後、頭や腕などに血液を送る3本の血管を枝分かれさせながら弓状に左後方へと大きく曲がり、背骨の前面に沿うようにしながら腹部方向へと下っていきます。大動脈にはいつも血圧がかかっているので、動脈硬化などで弱くなった部分があると、大きな問題が起こってきます。具体的には、血管の壁が薄くなって大きく膨らんでくる「動脈瘤」、大動脈の壁が裂けてしまう「大動脈解離」などがあります。問題が生じた部位によって、胸部大動脈瘤、腹部大動脈瘤などと称されます。当院では、動脈瘤・大動脈解離・動脈硬化症などの治療を行います。さらに、大動脈手術後の治療やケアについても対応いたします。
腫瘍関連循環器
- このような患者様は当院をご受診ください
- 抗がん剤関連心筋症・心不全 など
医学の進歩により多種多様なメカニズムの抗がん剤が開発されております。一方でそれら抗がん剤が心臓に悪影響を引き起こし、息切れ・むくみなどの心不全を誘発することも報告されております。そのため、当院ではがん患者の方を対象として、採血検査や心臓超音波検査で診断を進めます。そのうえで、がん治療による副作用で心不全などを発症してしまったことが分かったときは、必要な治療を行います。必要があれば、抗がん剤処方されている診療科に抗がん剤継続可否について相談させていただくこともあります。
先天性心疾患
- このような患者様は当院をご受診ください
- 心房中隔欠損症、心室中隔欠損症、卵円孔開存症 など
先天性心疾患とは、生まれつき心臓や血管の一部に異常がみられている病気の総称です。主に妊娠初期から中期の胎児の段階で心臓などの形成に異常が生じると、出生後に血液を全身に送れなくなったり、大動脈を通る血液に十分な酸素が含まれなくなったりします。先天性心疾患のなかには、成長とともに自然に治るケースもありますが、その一方で命に関わるケースもあるため、乳児健診などで心臓や血管の異常を指摘されたときは、さらに詳細な検査を受けることが大切です。当院では、心房中隔欠損症、心室中隔欠損症、卵円孔開存症をはじめとして、様々な症例に対応しておりますので、まずはお気軽にご受診ください。
肺動脈血栓塞栓症など
- このような患者様は当院をご受診ください
- 肺動脈血栓塞栓症・深部下肢静脈血栓症・エコノミークラス症候群・肺高血圧・慢性肺血栓塞栓症 など
肺動脈血栓塞栓症は、主に静脈系から流入した塞栓子が原因となり、肺動脈を閉塞させてしまう病気です。肺動脈内で形成された血栓によって引き起こされることもあります。これによって低酸素血症の状態になったり、肺高血圧の原因になったりすることもあるので、注意が必要です。最近は治療成績が向上傾向を示していますが、依然として生命に直結するケースも少なくないです。そのため、必要に応じてお薬による治療や、手術的血栓除去などを行います。当院では、肺動脈血栓塞栓症・深部下肢静脈血栓症・エコノミークラス症候群・肺高血圧・慢性肺血栓塞栓症などの検査診断治療を行うことができます。急を要する病状のこともありますので、お気軽にご相談ください。
閉塞性動脈硬化症
閉塞性動脈硬化症は、動脈硬化によって血管が狭くなったり、血管が詰まったりすることで引き起こされる病気のひとつです。主に下肢の動脈硬化が原因となりますが、そのほかの部位に生じることもあります。初期の段階では目立った症状がみられないこともありますが、末梢部分に循環障害を起こしているため、酸素や栄養を十分に送り届けられない状態が続きます。そのため、進行するにつれて冷感、しびれ、足の痛み、潰瘍、壊死といった症状が強まります。患者様のなかには、血栓が形成されることによって急速に悪化するケースもあります。お気軽にご相談ください。
感染性心内膜炎
感染性心内膜炎は、虫歯やアトピーなどが原因で外部から血液内に細菌が入り込み、心臓に炎症を起こす疾患です。原因不明の発熱などとして発見が遅れることもあり、息切れ・むくみなどの弁膜症、心不全の症状や、脳梗塞などの原因となることがあります。早期に治療を行わないと命に直結することもあります。長期間持続する発熱や、原因不明の炎症が継続しているときは、感染性心内膜炎の可能性もあるため、なるべく早い段階で医療機関を受診することが大切です。当院の循環器内科では、血液検査や心臓超音波などで鑑別診断を行います。持続する発熱などがある場合は、当疾患も命に影響を与えるため鑑別検査が必要となります、お気軽にご相談ください。
起立性低血圧
起立性低血圧は、起立したときの血管収縮反応がうまくいかないことが原因となり、血圧が低下してしまう病気です。これに伴い、立ちくらみ、失神などの症状が出現します。症状が重いケースでは、吐き気や視覚障害を伴うこともあります。起床時に頭がふらついたり、立ち上がったときに意識が遠のいたりしたときは起立性低血圧の可能性が考えられるので、念のため、循環器内科を受診されるとよいでしょう。
心タンポナーデ
心臓を覆っている膜を心膜といいます。心膜と心臓の間に液体がたまり心臓機能を阻害し、息切れ・むくみなどの心不全症状を引き起こすことがあります。心臓超音波などで鑑別診断を行います。
◎当院では、心血管疾患に対する迅速採血検査や、超音波検査、レントゲン、心電図、動脈硬化判定検査などが可能です。お気軽にご相談ください。