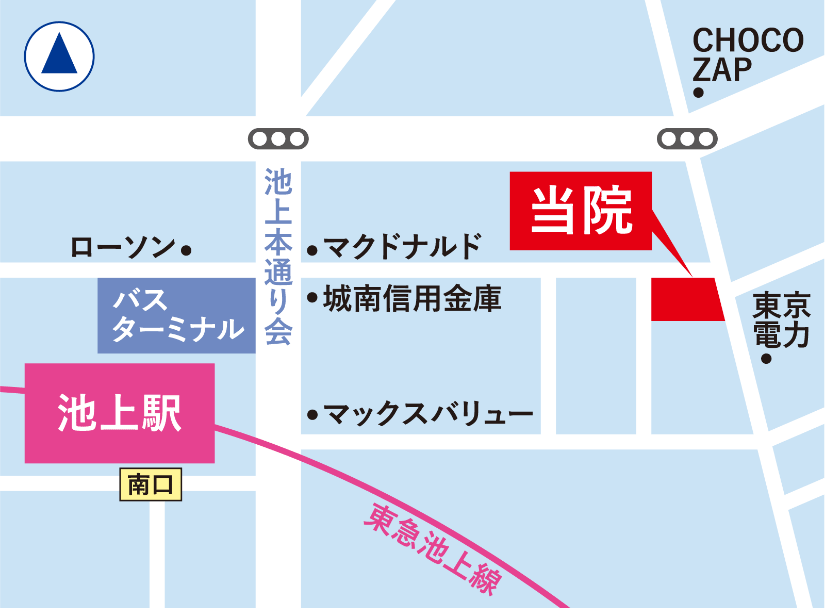内科で扱う主な疾患・症状
- 風邪・主な発熱感染症
- 急性上気道炎・インフルエンザ・新型コロナウイルス・マイコプラズマ
風邪
風邪とは、様々な病原体が鼻から喉、気管の入り口にかけての空気の通り道に感染し、それらの部分に炎症を起こしている状態であり、症候群としての分類となります。多くの場合、ウイルスによる感染が主な原因となります。症状に関しては、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、喉の痛み、咳、痰、頭痛、発熱などが代表的です。そのほかにも、嘔吐、嘔気、下痢、腹痛などの消化器症状を伴うことがあります。比較的に軽い症状のことが多く、通常は1週間以内に症状が改善していきます。
急性上気道炎
急性上気道炎は、解剖学的感染部位による分類で、診断的分類となります。上気道に様々な病原体が感染し、この部分に炎症を起こしてしまいます。原因のほとんどはウイルスで、代表的なものにはライノウイルス、コロナウイルス、RSウイルス、インフルエンザウイルス、アデノウイルスなどがあります。主な症状は、高熱、ひどい咳、咽頭痛、くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、咳、痰、頭痛、発熱などです。患者様によっては、嘔吐、下痢、腹痛などの消化器症状を伴うこともあります。
インフルエンザウイルス・新型コロナウイルス・RSウイルスに対しては予防接種も有効です。ご相談ください。
インフルエンザ
インフルエンザウイルスに感染することで発症する病気です。一般の風邪と比べると症状は重いのですが、通常は症状が3~7日間続いた後、治癒に向かいます。ただし、気管支炎や肺炎を併発しやすく、脳炎や心不全に至ることもあります。とくに、高齢の方や基礎疾患のある方はリスクが高いので十分な注意が必要です。主な症状としては、高熱、悪寒、頭痛、関節痛、倦怠感などの全身症状があります。風邪症候群と同じように、咳、痰、呼吸困難、腹痛、下痢などもみられます。
新型コロナウイルス
新型コロナウイルスに感染すると、人によっては重症化し、命に影響することもあります。とくに高齢者や基礎疾患のある方は重症化のリスクが高いとされているので、各自治体では高齢者などを対象にした新型コロナワクチンの定期接種を推奨しています。感染経路については、接触感染、接触感染のほか、エアロゾル感染も挙げられます。主に2~7日の潜伏期間を経てから発症するようになります。主な症状は、高熱、咳、痰、喉の痛み、全身の倦怠感、息切れ、嗅覚や味覚の異常などです。症状が悪化すると、強い呼吸困難に陥ってしまい、入院治療が必要なることもあります。
マイコプラズマ
マイコプラズマという細菌に感染することにより引き起こされる病気です。お子さまや若い人に比較的多いといわれています。インフルエンザなどのように広範囲で集団感染することは少ないのですが、渇いた咳が止まらなくなり、長期間にわたって影響がでることもあります。とくに高齢者が感染すると、生命に危険が及ぶケースがあるため、注意が必要です。1年を通じてみられますが、冬にやや増加する傾向があります。
倦怠感・息切れ
健康な方でも、激しい運動を行ったときは息苦しくなり、息切れします。しかし、身体に過度の負担をかけていないのに呼吸が乱れるのは、心臓、肺、貧血などに何らかの異常が生じている可能性があります。長期間にわたって倦怠感が続いているときも、早めの対応が必要になります。倦怠感や息切れを放置していると、循環器や呼吸器などの重大疾患リスクが高まりかねません。まずは当院を受診し、治療の必要性をご確認ください。
頭痛
頭痛の原因は大きく2つに分けられます。一つ目は、命に別条はないとされる「一次性頭痛」です。具体的には、片頭痛や緊張型頭痛、群発頭痛などがあります。このうち片頭痛は、頭の片側もしくは両側にズキンズキンと感じる痛みが生じます。痛みの頻度は様々で、週1の方もいれば、月に1、2回という方もいます。患者様によっては、頭痛が起きる前に視野の一部が見えにくくなる、フラッシュのような光が目の前で瞬くといった前兆が見られることもあります。 近年は、内服で効果が乏しい場合などは注射薬なども選択肢となります。ご相談ください。
緊張型頭痛は、頭や首の筋肉が緊張、収縮することで起きる頭痛です。同じ姿勢を長時間続けていると、肩こりや首のこりなどの血行障害によって頭痛が引き起こされることがあります。とくに、日頃からのストレスを抱えている方に起こりやすいです。主な症状は、首から後頭部にかけての痛み、頭が締め付けられるような痛みなどです。めまいや立ちくらみが起きることもあります。
群発頭痛は、目がえぐられるような痛みが片側の目のくぼみの部分からこめかみにかけて生じるタイプの頭痛です。人によっては目の充血や涙、鼻みずなどが見られることもあります。お酒を飲み過ぎる方、タバコを吸われる方に多いのも特徴です。群発頭痛は、いったん起きてしまうと、比較的に長期にわたって症状が続きます。
二つ目は、脳腫瘍や脳梗塞、髄膜炎などの病気の一症状として現れる「二次性頭痛」です。この場合、すぐに治療が必要なケースもあります。慢性的な頭痛に悩まされて来院されるという患者様は、一次性頭痛と診断されることが多いですが、二次性頭痛の可能性も考えられます。頭痛が気になる方は、なるべく早い段階で医療機関を受診するようにしてください。 病状に応じて高次医療機関にご紹介いたします。
認知症
認知症は、一度正常に発達した脳の知的機能が、加齢などの要因によって低下してしまう病気です。患者様にもよりますが、もの忘れが多くなる、今いる場所や時間が分からなくなる、理解や判断能力が著しく低下するといった症状が現れます。これに伴い、家事や仕事に影響が出たり、身の周りのことができなくなったりします。性格が変化し、怒りっぽくなるなどの症状が出ることもあり、家族関係や社会生活にも大きく支障をきたしてしまいます。
なお、認知症には様々な種類がありますが、とくに多いのがアルツハイマー型認知症です。この場合、加齢に伴ってアミロイドベータという蛋白が徐々に脳に溜まり、神経細胞が障害されます。そのため、記憶障害などの認知機能低下が起こってしまうのです。進行するにつれて神経が死滅していき、さらに脳そのものも萎縮して、その脳に司令を受けている身体機能も失われていきます。
認知症は早期に発見し治療することで、進行を遅らせる可能性もありますので、ものの名前が思い出せなくなった、同じことを繰り返す、妄想がある、外出すると家に帰ってこられなくなるなどの症状がみられたときは、お早めに当院をご受診ください。
不眠
寝たくても眠れない状態の方は、不眠状態になっていると考えられます。これは睡眠障害の一種であり、心配事やストレスがあってなかなか寝付けないというケースや、何らかの疾患が影響しているケースが多いです。寝つきが悪くて睡眠不足が続くようになると、日中の活動している時間帯にも影響を及ぼすようになります。寝つくまでに時間がかかるようになった、いったん寝入っても夜中に何度も目が覚める、かなり早く目覚めるようになった、睡眠時間は確保しているが眠りが浅い、よく眠れないことでイライラするなどの症状がみられるときは、治療を受けるようにしてください。
脳卒中
脳卒中は、脳の血管に障害が現れる病気の総称です。具体的には、脳の血管が詰まることで引き起こされる「脳梗塞」、脳内の血管が破れてしまう「脳出血」、脳を保護している薄い膜と軟膜の間に出血が起こる「くも膜下出血」などがあります。こうした疾患が突然に起こると、生命の危機に直面することもあります。
片側の手や顔に麻痺や痺れが現れた、呂律が回らなくなった、他人の言葉が理解できなくなった、うまく歩けなくなった、片側の目が見えなくなった、これまで経験のないような激しい頭痛が起こったなどの症状がみられたときは、すぐに救急車を呼ぶか、当院をご受診ください。診察、病状に応じて高次医療機関をご紹介いたします。
慢性腎臓病
慢性腎臓病は、何らかの腎障害によって腎臓の機能が慢性的に低下している状態です。初期の段階では、自覚症状があることはほとんどないため、人間ドックや健康診断によって腎障害の有無を確認しておくことが大切です。放置していると、腎機能がどんどん低下していき、体にとって不要な毒素や水分を体外に出すことができなくなります。また、骨や筋肉、血液など体にとって必要なものを作り出す働きも低下していきます。それにより、夜間尿、むくみ、貧血、倦怠感、息切れなどの症状が現れてきます。
さらに、心筋梗塞、狭心症、心不全、不整脈、脳卒中、貧血、筋力低下、骨粗鬆症、脂質異常症、高尿酸血症などを発症することもあります。機能低下がさらに進んでしまうと、透析や腎移植が必要な状態まで進行してしまう場合も少なくないです。 近年は、慢性腎臓病に対する症状進行抑制のための内服も推奨されています。ご相談ください。
睡眠時無呼吸症候群
睡眠時無呼吸症候群は、睡眠時に呼吸停止または低呼吸になる状態のことをいいます。このなかには、喉の周辺における空気の通り道が塞がることで呼吸が一時的に停止する「閉塞性睡眠時無呼吸症候群」と、脳から呼吸指令が出なくなることで起こる「中枢性睡眠時無呼吸症候群」があります。前者の場合は、首の周囲にたくさん脂肪がついている、舌が大きい、扁桃や口蓋垂が大きい、あごが小さいといった原因が考えられます。お酒を飲み過ぎる方、タバコを吸われる方にもよく起こります。一方、後者の中枢性睡眠時無呼吸症候群の場合は、肺や胸郭、呼吸筋、末梢神経には異常はありませんが、呼吸指令がでないことで無呼吸が生じます。いびきがうるさい、疲労感がある、日中に強い眠気がある、朝起きると体が重たいなどの症状があるときは、睡眠時無呼吸症候群の可能性があるので、お早めに当院をご受診ください。
膀胱炎
膀胱炎は、文字通り膀胱に炎症が起こる病気であり、とくに若い女性に多いといわれています。女性の外陰部にいる細菌が尿道から入って膀胱粘膜で繁殖すると膀胱炎になりやすいです。通常は菌が入っても、膀胱の感染防御機構がはたらいて膀胱炎にはなりませんが、ストレス、体調不良、冷え症、尿を我慢し過ぎる、1日の尿量が少ない、不潔な性行為などがあると、発症リスクが高まります。主な症状は、排尿痛、排尿時違和感、頻尿、残尿感、下腹部痛、血尿、混濁尿などです。治療に関していうと、抗生剤を3~5日間ほど内服します。これによって治癒することが多いです。
急性腹症
急激にお腹が激しく痛んだときは、急性腹症によって緊急手術が必要になることがあります。具体的には、胃や十二指腸の穿孔、虚血性腸炎、腸重積、虚血性腸炎、胃がんや大腸がんの穿孔、ヘルニア嵌頓、急性虫垂炎、憩室炎の穿孔、肝臓がんの破裂、急性肝炎、急性胆嚢炎、胆石発作、急性膵炎、脾破裂、尿路結石、腎梗塞、腹部大動脈瘤破裂など様々なケースがあるので、すぐに当院を受診し、必要な検査を受けるようにしてください。
熱中症
熱中症は、気温の上昇や過度な運動などによって体温が上昇し、そのことが原因となって様々な健康障害が起こった状態です。患者様によっても異なりますが、軽症の場合は筋肉痛やめまいなどの症状がみられます。中等度になると、頭痛や嘔吐、嘔気、全身の倦怠感が現れます。重症の場合は、全身のけいれん、意識障害、高体温などの症状が起こり、生命にかかわることもあります。なお、熱中症というと、高温多湿の夏季に生じるイメージが強いと思います。実際、暑さによって体温調節機能が乱れてしまい、熱中症になることがよくあります。しかし、季節に関係なく体内の水分量や塩分量のバランスが崩れることでも起きます。とくに冬は、乾燥しやすい季節でもあり、水分補給をおろそかにしがちです。そこから脱水症状が起き、さらに放置が続けば熱中症を発症することもあります。 病状に応じて点滴対応も検討いたします。
花粉症
花粉がアレルギー症状を引き起こすアレルゲンとなる季節性のアレルギー性鼻炎のひとつです。花粉を吸いこむと、鼻の粘膜に花粉が付着し、このことが原因となって鼻水やくしゃみ、鼻づまりなどの症状があらわれます。このほか、目のかゆみを引き起こしたり、皮膚にかゆみを伴う発疹などの症状が現れたりすることもあります。花粉が飛散する時期になると、仕事や勉強に集中できず、夜よく眠れなくなったり、昼間に眠気や倦怠感などの症状が現れたり、集中力が低下して仕事に支障をきたしたりします。そのため、お薬による治療を行い、花粉症による症状を減らしていきます。
蕁麻疹
痒みが強く、丸っぽい形をし、わずかに盛り上がったミミズ腫れが出現する疾患です。蕁麻疹は数分~24時間以内に消えていくのですが、再び発疹ができることもあります。痒みを伴うことが多いのですが、患者様によってはチクチクとした痛み、熱く焼けつくような痛みが生じることもあります。蕁麻疹の治療には、抗アレルギー薬や抗ヒスタミン薬などを用います。多くの場合、薬物治療を開始してから数日程度で症状が治まりますが、その後も医師の指示に従って飲み続け、徐々に減らしていくことが大切です。
貧血
貧血は、血液中に含まれるヘモグロビンが少なくなってしまい、全身に十分な酸素を供給できなくなってしまった状態です。例えば、ヘモグロビンをつくるための材料である鉄が欠乏すると鉄欠乏性貧血が起こります。また、ケガや病気のために血管が破れて出血すると、血液が失われるため出血性貧血となります。主な症状としては、めまい、立ちくらみ、動悸、息切れ、疲れやすいなどがあります。
骨粗鬆症
骨が弱く、もろくなってしまい、ちょっとしたことで骨折するようになる疾患です。加齢によって骨の新陳代謝のバランスが崩れ、骨を形成するスピードよりも骨を破壊し吸収するスピードの方が速くなってしまうと、骨粗鬆症になりやすいです。この新陳代謝には女性ホルモンであるエストロゲンが関わっており、閉経にともになって分泌量が減ることで骨量が低下するため、高齢の女性に起こりやすいと考えられています。骨粗鬆症は、それ自体には自覚症状が無いため、検査によってなるべく早めに発見し、薬剤にて進行を抑制させることも重要になります。
失神
大脳皮質全体、あるいは脳幹の血流が瞬間的に遮断されることによって起こる一過性の意識消失発作です。一時的に血圧が低下して心臓から脳に送る血液量が少なくなり、脳全体が酸素不足なって意識を失ってしまいます。通常は数分以内に回復し、意識障害などの後遺症を起こすことはありません。